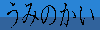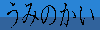一年前と変わったこと。
背が4cm伸びた。髪をショートにした。眼鏡をかけるようになった。一人の食事の味を知った。流れ星に願いを込める年ではなくなったけれど。
流星群と笑う鬼 林数雲
全国的な異常気象は、日本中をくまなく熱し、ここ南青山駅も例外ではなかった。この昼下がり、私はただバスを待っていた。時刻表は字が細かくて読めないが、バスは30分おき、もう来てもいい頃だ。
中学のとき、体育は英語の次に嫌いな授業だった。そんな私がなぜか高飛びで150cmを跳んだ。先生に頼まれて大会に出た。皆、背面とびで私だけがはさみとびだった。
青山山。アオヤマサンと読む。あそこに見える山。新興住宅地は名前のセンスが適当だ。何々銀座とか、何々原宿とか。ここ青山も、元はどんな名前だか、実は私も知らない。
「来年の今日、この場所で」真史はいった。
「遠くの学校でも星は見えるけど」
と、一筋の光。ぼそぼそと何か呟いている真史。
「3回いうと、叶うんだって」
真史は緊張するとよく喋る、その時に気付いた。
もう1時間は待っている。通りすがりのお兄さんにきいてみた。
「あの、今度のバスは何時に来るのですか?」
「バス?」通りすがりのお兄さんは、不思議そうな顔をした。私は無言でバス停の立て札を指さした。
「1時間500円だって、安いねえ」兄さんはうれしげにいった。
眼鏡をかけてよく見ると、バス停かと思ったのは昨日オープンしたカラオケボックスの立て札だった。「15日までだから早く行かなきゃね」兄さんの声が聞こえたが私はそれどころではなかった。
ここは私の知っている青山ではなかった。すべてが変わっていた。駅も、店も。古本屋は自転車置き場に、酒屋はコンビニに。レコード店はゲームセンターに。
その時、けたたましい音を立てて、バイクが私の目の前に止まった。黒ずくめの少年が、私に無遠慮に近付いてきた。
「春ちゃん、やっぱり困ってた。今日帰るってきいたから」
私はバイク少年に知り合いはなかったので黙っていた。しかし、なぜ彼は私の名前を知っているのか。
「真史」
私がつぶやくのと彼がヘルメットをとるのと同時だった。
喫茶店の店内。真史はコーヒー、私は紅茶とトーストを頼んだ。
真史はバイクの話を楽しそうに続けていた。
「どのエンジンがこう」
「この駆動系がどう」(あまり覚えていない)
私は黙ってトーストを食べていた。昼食を取っていなかったので。
ほとんど推薦で高校に入った以上、陸上部に入ることは暗黙の了解だった。学校の寮は門限が厳しく、窓から星を見ていた。そんな態度だったので、練習にはあまり参加せず、陸上部より天文部の方が、知り合いが多いありさまだった。
「それに、いくらやっても背面とびはできなかったしね」
いってから、われながらやけにおかしくなった。
私はベットの上で横になっていた。ラジオの声がきこえる。
「天才でーす」「人災でーす」
「二人あわせて天才・人災でーす」
この二人の18番は宮沢賢治のコントだ。調査室で一人の男が尋問されている。男は最初は認めないが、仏の源さんの登場で、本当は自分も宮沢賢治のことが好きなことを認めてしまう。
母の声が聞こえた。
「真史くんも背、高くなっちゃってほれ直した?」
「母さん、今夜ペルセウス座流星群だから」
「あんたたちは昔から、やれハレー彗星だ、やれ土星の輪だってね」
「真史は今頃、峠を攻めてるわ」
「でも私は自分で”てんさい”だと思うんです」
「天の災いか?」
「いえ、才能の災いです」
「そりゃ”さいさい”やんかー」ラジオが笑ってた。
心はどしゃぶり、外もいつの間に雨が降りだした。
表で排気音がした。「春香、真史君よ」母の声。かっぱを来て玄関に立つ真史。
「何」自分でも声が震えているとわかった。
「カラオケ行かない、ねえ」
「はぁ」イントネーションは上に、呆れているときの声。
繁華街を離れた山の上にカラオケボックスはあった。全五階建て。
「今日は歌い倒すよ」なかばやけ気味だ。
「オープン記念で安くなってんだ」うれしそうな真史。
本当のことをいうとカラオケは好きではなかった。
二三曲歌ううち、案の定帰りたくなってきた。
一時間五百円。二時間ならば千円。三時間なら、想像もできない。
「あたし帰る、送って」嫌な女だと思った。
「まって、もう1時間あるから」
「こんなはずじゃなかった…、青山も、真史も」もう涙声になってる。
突然、真史が私の腕を取り、非常階段を駆け登った。
屋上の重たい扉を押すと、そこは満天の星。
「ここは…」
「夜半過ぎには晴れるっていってた」
「ここは日本で三本の指に入る星の名所。自殺の名所でもある」
「…」
「5等星だってこの通り。しかしそれも目がいいとしての話、…ごめん」
「ううん、あっ流れ星」
「春香……。それは飛行機」
「入場券買うと、キセルと思われるんだよな、絶対」
真史がさっきから鉄道の悪口を続けている。
「だいたい、電車には乗らないのにこの値段だ」
「毎年のように値上がるし」と、真剣な表情になった。
「春香…、ちゃん。来年も流星群は来るけど、君は」
「来年のこというと鬼が笑うよ」
そう言って電車にとびのった。
真史の声が軽快なメロディにかき消される。
変わるもの。変わらないもの。
洋酒の広告のような文句がふっと浮かんだ。
電車は走る。少し冷房がききすぎる。
来年も青山は暑いだろうか、と声に出した時、どこかで鬼が笑った。